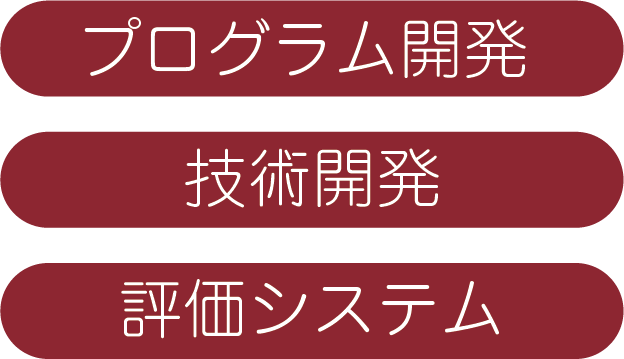
今回は、プログラム開発・技術開発・評価システムの3つの分科会の合同分科会とし、伝統的な地域文化活動のアップデートとテクノロジーによる活動創出、その可能性と課題について議論を深めました。
PRESENTER
●AnCo分科会 紹介
溝内 辰夫(AnCo事務局長)
●プログラム開発分科会
大江 匡行 氏(京都市中京区/日彰自治連合会 副会長・医仁会武田総合病院医工連携推進室)
●技術開発分科会、評価システム分科会
清古 貴史 氏 (リアルワールドゲームス株式会社 CEO)
-AnCoを創るために必要な3つのレシピ:3つの分科会が目指すもの
溝内 辰夫(AnCo事務局長)
今回は「安寧社会共創イニシアチブ」、略称 AnCo(あんこ)の第1回分科会です。初回となる今回は、どのような分科会を行うのかを簡単にご説明いたします。AnCoにある4つの分科会のうち3つに焦点を当て、「あんこ」にちなんで“3つのレシピ”としてご紹介します。
AnCoでは、社会とのつながりが安寧社会を築く上で重要であると考えています。研究によると、社会的なつながりは禁煙や禁酒よりも健康に良い影響を与え、逆に孤立は飲酒や喫煙以上に健康リスクを高めることが明らかになっています[1]。
従来の医療は心身の状態に着目してきましたが、近年では社会的要因が健康に与える影響も注目されています。特に「社会とのつながり」の重要性は認識されているものの、その定義や種類、評価方法についてはまだ十分に解明されていません。AnCoでは、これらの課題について分科会で議論を深めていきます。
安寧社会共創イニシアチブ(AnCo)の3つの主要な分科会は、社会とのつながりを通じて安寧社会の構築を目指しています。
1.プログラム開発分科会
地域活動に潜在する健康や幸福を高める要因と阻害要因を特定し、本質的価値を尊重しながら、既存プログラムの改良や新規活動プログラムを開発する。
2.技術開発分科会
活動の効果測定や個人に適した活動をレコメンドするプラットフォームを検討し、テクノロジーを活用して地域活動への参加を促進する。
3.評価システム分科会
地域活動群が地域や社会に与える好影響を測定し、活動の価値を可視化する。
+ これらの取り組みを横断的に支援する空間デザイン分科会
これらの分科会を通じて、AnCoは地域活動の潜在的な健康や幸福を高める機能を引き出し、社会とのつながりを強化する具体的な方策を開発・実装することを目指しています。
【WEB掲載用】AnCo分科会Vol.1_AnCo
― 祭りを通じた地域のつながりと再生
大江 匡行 氏(日彰自治連合会 副会長)
祇園祭は、日本三大祭の一つであり、その歴史は平安時代にまで遡ります。貞観11年(869年)、国内で疫病が流行した際に“66本の矛”を立てて神輿を送り、国家の安寧と厄災消除を祈願したことがその起源とされています。祭りは、氏神を祀る『神社の祭り』と、地域コミュニティによる『町衆の祭り』が融合し、まちの絆を深める大切な役割を担っています。
祇園祭は八坂神社の氏子地域で行われ、東山区、中京区、下京区にまたがる25の学区で構成されています。この「学区」は、明治維新後に「まちづくりは人づくりから」という理念のもとできた、「番組小学校」が起源です。番組小学校は、地域住民の寄付“竈金(かまどきん)”によって支えられたため、単なる教育機関にとどまらず、区役所・保健所・消防署・警察署の役割も果たす地域の総合センター、“自治の単位”として機能していました。
八坂神社の氏子地域の一つである「日彰(にっしょう)学区」は、約3,000人、約1,500世帯の住民が暮らし、62の町内会が連携する自治組織を持っています。しかし、少子高齢化や住環境の変化により、地域活動への参加者が減少し、自治会の人材不足が深刻な課題となっています。特に、マンションやアパートの増加により、住民の約8割が集合住宅に住む現在、新しい住民と昔からの住民が関わる機会は少なく、「オートロックによる物理的な壁」や「マンション管理規約の制約」などが、地域とのつながりを妨げています。このような状況の中で、住民の地域参加を促す仕組みづくりが求められています。
祭りを通じて新たなつながりを生み出し、地域の再生を図ることが重要です。学区を超えた広い視点で、祭りを軸に「役割づくり」「人づくり」「まちづくり」を進め、より安寧な社会を創出していくことが今後の大きな課題となっています。
-リアルとバーチャルの融合でWell-being向上と地域の活性化
清古 貴史 氏 (リアルワールドゲームス株式会社 CEO)
弊社は、歩くことで健康寿命を延ばし、充実した人生を提供することを目指しています。全国のユーザーが位置情報や写真データをバーチャルマップに投稿・閲覧できる独自の3D地図エンジンを活用し、観光・健康・防災に役立つコンテンツを地図アプリで提供しています。これは、地域の価値ある資源を収集・再発見する「地域資源のアップサイクル」により、ソーシャルキャピタルの可視化を実現します。この地図を活用することで、人と地域の“つながり”をさらに加速させていきたいと考えています。
実際に、住宅地などのアトラクションが少なく長時間の歩行が見込めない地域においても、デジタル地図上に演出やゲーミフィケーションの要素を取り入れることで、自然と歩行時間が延び、地域を巡るユーザーの行動変容が確認されています。鉄道系位置情報アプリ「トレイントレイン」では、全国の廃線を歩く体験が可能です。ユーザーは、電車に乗っている感覚で駅や乗客を集めながらプレイし、ゲームを楽しみながら移動することで、行動変容を促します。また、地域の魅力を再発見できるアプリでは、住民も普段訪れない史跡や、住職の話を聞きながら巡るツアーを通じて、地域にゆかりのない人々にも歴史や学びの場を提供する機会を生み出しています。
リアルワールドゲームス株式会社 CEO 清古 貴史 氏
AnCoの活動を通じて、以下の3つの要素が交わる“ソーシャルキャピタルが豊かな場所”を可視化し、地域資源の再発見につなげることで、人々がより気軽に地域活動へ参加できる環境を整えていきたいと考えています。
「見える化」:3D地図上にソーシャルキャピタルや文化的資本になる場を表示する
「ポイント化」:評価を元に幸福度や健康度が上がる行動に対してのインセンティブを付与する
「ゲーミフィケーション化」:歩行や通いの場へ移動をする等、行動のモチベーション(動機付け)を維持させる
この事業を持続的に展開するためには、安定した収益基盤が不可欠です。その手段の一つとして、成果報酬型の事業プログラム(PFS・SIBなど)の活用が求められます。日本国内でも、成果連動型の施策は適正化が進んでおり、経済産業省も積極的に推進しています。弊社は、事業者を統括するプラットフォームの運営を担うことで、自治体・サービス事業者・第三者評価機関が従来手作業で行っていたプロセスの自動化を実現します。さらに、地図を活用した可視化により、住民に新たな体験を提供するとともに、管理者が成果を明確に把握できる仕組みを構築していきたいと考えています。
【WEB掲載用】AnCo分科会Vol.1_RWG-1


